セッション用Backing Trackはこちら

ALBIT (1) BEHRINGER (1) Benson Amps (2) Blackstar (3) Bogner (4) BOSS (5) Cornerstone (3) Crazy Tube Circuits (4) Darkglass Electronics (2) DigiTech (1) Dumble (2) E.N.T EFFECTS (2) EarthQuaker Devices (2) electro-harmonix (7) Empress Effects (2) Eventide (1) EVH (2) Fender (8) Free The Tone (3) Friedman (3) Fryette (2) Fulltone (1) Gibson (1) Henriksen (1) HOTONE (4) IK MULTIMEDIA (4) Jackson Audio (1) James Tyler (1) JHS PEDALS (3) Keeley Electronics (8) KEMPER (3) KERNOM (1) klon (2) Laney (1) Limetone Audio (2) Line6 (5) LPD Pedals (1) Mad Professor (1) Magnatone (2) Marshall (5) MESA/BOOGIE (3) Morgan Amplification (1) Morningstar (1) MXR (2) Neural DSP (3) One Control (3) Origin Effects (1) Ovaltone (2) Paul Reed Smith (5) Pedaltrain (1) Positive Grid (2) Revv Amplification (1) Science Amplification (1) Soldano (2) strymon (8) Suhr (7) Sunfish Audio (1) Supro (2) tc electronic (5) TECH21 (1) Tom Anderson (1) Tone King (1) TONEX (2) Two Notes (1) Umbrella Company (1) Universal Audio (4) VALETON (1) VEMURAM (7) Victory Amps (3) Virtues (3) Vox (1) WALRUS AUDIO (4) Wampler (6) Warm Audio (3) Xotic (10) YAMAHA (2)

「ロックの歴史を変えたアンプは?」と問われれば、多くのギタリストが Marshall 1959“Plexi” の名を挙げるでしょう。100Wのフルチューブ回路から放たれるあの図太いクランチは、ジミ・ヘンドリックスやクラプトン、ヴァン・ヘイレンらを通じて世界中のステージとレコードに刻み込まれてきました。
そんな伝説の回路をベースに、本家マーシャルが現代的モディファイを施した限定モデルが 「1959MS」 です。オリジナルの良さはそのままに、マスターボリュームやクリッピング回路を追加して自宅練習からアリーナ級ライブまで幅広くカバー。
本記事では、まず 1959が誕生した背景と系譜 を振り返り、続けて1959MSがどこをどう進化させたのかを詳しく解説していきます。伝説のトーンを求めるクラシック派も、実用性を重視するモダン派も、ぜひ参考にしてみてください。

1959というモデル名は“1959年製”を意味するわけではありません。マーシャル初号機 JTM45(1962)から始まる型番体系の一つで、1967年に100W仕様へ発展したモデルが1959 Super Lead 100でした。
ベースはJTM45の回路を100Wへ拡張した試作段階。パワー管はKT66×4、トランスはドラメット製。ザ・フーのピート・タウンゼントが大音量を求めメーカーに直訴したことが開発のきっかけ。
ゴールド‐アクリル(プレキシガラス)パネルを採用した初期100Wヘッドが登場。プリアンプにECC83×3、パワー管をEL34×4へ変更し、よりアグレッシブなハイミッドが得られるサウンドに進化。ジミ・ヘンドリックスがモンタレーやウッドストックで使用したのもこの時期の個体。
コストと耐久性の理由でフロントパネル素材を金属へ切替。音の方向性は同じだが“Plexi”と呼ばれるのは67-69年のアクリル期を指すのが一般的。アンプ背面の配線方式もハンドワイヤードからPCBへ移行。
“Plexi 20周年”を記念してリイシューが発売。真空管や部品の規格が現代仕様になったほかマスターボリュームは非搭載。1990年代~2000年代のリバイバル・ロックブームを支えた。
そして2025年――マーシャルは自社工場でモディファイを施した 1959MS をリリース。オリジナルと同じハンドワイヤード基板を土台に、


Marshall 1959MSの基本情報
| タイプ | 改造(Modified)シリーズ 限定アンプヘッド |
| 定格出力 | 100W(オールチューブ) |
| チャンネル | 2チャンネル(4インプット、EQは共有) |
| 真空管 | プリアンプ: ECC83 ×2 + ECC83 ×1(位相反転用)、パワーアンプ: EL34 ×4 |
| 搭載モディファイ | マスターボリューム、ブライトスイッチ、クリップスイッチ(ON/OFF+2タイプ切替) |
| スピーカー出力 | 1/4″スピーカーアウト ×2(インピーダンス切替: 16Ω/8Ω/4Ω) |
| 本体サイズ・重量 | W740×H305×D210 mm・約21.4 kg |
| 発売時期(予定) | 2025年8月23日(※マーシャルショップ先行受注) |
| 参考税込価格 | 770,000円(メーカー希望小売価格) |
Marshall 1959MSは、基本となる回路に1959HW(ハンドワイヤード版)の基板を用いた真空管100Wアンプヘッドです 。クラシックな2チャンネル(4インプット)設計と真空管構成はオリジナル同様で、プリアンプ管にECC83を3本(※位相反転用1本を含む)、パワー管にEL34を4本搭載しています。
一方で本機ならではのモディファイ機能として「マスターボリューム」や「ブライトスイッチ」、**「クリッピング回路(ON/OFFと2種類の歪みタイプ)」**が新設され、背面には16Ω/8Ω/4Ω切替対応のスピーカーアウト(1/4インチ×2)を備えます。



マーシャル1959MS最大の特徴は、「伝説のPlexiサウンドはそのままに、現代の音楽シーンでも汎用性を高めた」点にあります 。オリジナルの1959が抱えていた課題(音量コントロールの難しさや歪みの不足など)に、本家マーシャルが自らメスを入れ改良を施したことで、ビンテージの味わいと実用性を高次元で両立しているのです。具体的な進化ポイントと音響上の特徴は次のとおりです。
1959MS最大の改良点がこれです。従来の1959はマスターボリュームを持たず、真価を引き出すには常識破りの大音量でアンプをクランクアップ(出力全開)する必要がありました。新搭載のMaster Volumeを時計方向いっぱい(10)に上げれば従来と同じ回路配列でオリジナル1959と同等の音量設定になり 、逆に絞れば自宅レベルの小音量でもパワー管を飽和させた歪みを得やすくなります。要するに**「音量と歪みの関係」を自在にコントロールできる**ため、深夜の練習から大音響が求められるステージまでシーンを問わず扱いやすくなりました 。
オリジナルのPlexiは歪みの強さで言えば現代のハイゲインアンプに遠く及ばず、ハードロック以上のジャンルではブースター/オーバードライブ・ペダルによる補強が定番でした。1959MSではアンプ内部にプリアンプブースト回路(Clipスイッチ)を組み込み、スイッチ一つでゲインブーストが可能です 。さらに歪みの質を選べるクリップタイプ・セレクターも備え、**モードI(ツェナー・ダイオード)とモードII(トランジスタ)**という2種類のクリッピング回路を切替えられます 。モードIでは「よりオープンでダイナミックレンジの広い歪み」、モードIIでは「よりコンプレッションが強く飽和感のある歪み」になるため 、クラシックなクランチからモダンなリードトーンまで幅広い歪みキャラクターをこの1台でカバーできます。ClipスイッチをOFFにすればブースト回路はバイパスされ、純粋なオリジナル1959相当の回路で鳴らすことも可能です。
Master Volumeの有効活用に合わせて追加されたのがBrightスイッチです。オリジナル1959を小音量で鳴らした際によく感じられる**「高音域が減衰してこもったように聞こえる」現象を補うための機能で、スイッチONにすると高域成分を強調して本来のPlexiらしいブライトなトーン**を蘇らせます 。特に自宅練習や録音時などMaster Volumeを絞った場面で有効で、微小音量でも腰のあるサウンドメイクが可能です。
オリジナルの4インプットPlexi同様、1959MSもチャンネルIとIIのブリッジ接続(ジャンパーケーブル等でリンク)による並列使用が可能です 。これによりBrightチャンネルとNormalチャンネルの2系統のプリアンプを同時に駆動でき、音に厚みと広がりを加えることができます。オリジナル1959ではプレイヤー自身が入力端子間をパッチケーブルで繋ぐ必要がありましたが、1959MSではインプット配置や内部回路の工夫によりリンクがより簡便になっている模様です 。従来からのテクニックも活かしつつ、更なる音作りの自由度が与えられています。
以上の改良によって、Marshall 1959MSはオリジナルの持つパンチの効いたUKロックトーンをそのままに、必要に応じてゲインブーストされたモダンサウンドまでシームレスに切り替えられる柔軟性を獲得しました 。音の傾向としては、クリッピングを使わない場合は往年のSuper Leadと同様に艶やかなクリーントーン~図太いクランチが持ち味で、ClipモードをONにすればJCM800以降の時代を彷彿とさせるハイゲイン・リードも難なくこなします。
「Masterをフル10にしてClipもOFFにすれば完全に従来通りの1959、そこから必要に応じて徐々にモダンテイストをブレンドできる」――まさに伝説的サウンドの懐の深さと拡張性を両立したアンプと言えるでしょう 。また、英国ブレッチリー工場で製造される本機は仕上げも非常に丁寧で、堅牢な筐体や美しい配線など随所にマーシャル伝統のクラフトマンシップが息づいています 。ビンテージMarshallファンにも安心して受け入れられるクオリティで、“音の要”たるオリジナル回路のサウンドキャラクターを損なうことなく時代に適応させた点が1959MS最大の魅力でしょう。
24:00〜
オリジナルのMarshall 1959がギターアンプの歴史における**「伝説」であることは疑いありません。そして1959MSは、その伝説を現代に甦らせアップデートする、いわば「伝説の再構築」という試みに他なりません。ビンテージ Plexi のサウンドキャラクターや魂はそのまま**に 、長年プレイヤーたちが求めてきた機能(マスター音量やゲインブースト)をメーカー自身が公式に盛り込んだ意義は大きいでしょう。事実、「従来の音色を忠実に再現しつつ、新機能で音の幅を拡張した1959MSは見事だ」という評価も専門筋から得ています 。Marshall社が自ら手掛けることで音質や工作精度の面でも妥協はなく 、オリジナルの持つ価値を損なうことなく進化させた点に、このアンプの真価があります。
確かに価格面のハードルは低くありません。しかし、それでもなお**「本物のマーシャル」が放つ改造Plexiという唯一無二の存在感は、コアなギタリストに強い魅力を放っています。クローンアンプやペダルでは代替し得ないブランドの重み、そして伝統と革新が融合したサウンド——1959MSはまさにMarshallが送り出す“伝説の再構築”と言えるでしょう。往年のファンにとっては夢のようなアイテムであり、次世代のプレイヤーにとってはマーシャルの遺産と未来を同時に手にできる逸品です。もしあなたが伝説的トーンへの憧れと現代的な実用性の両方を求めているなら、Marshall 1959MSはその期待をきっと裏切らないはずです。伝説を纏いながら最新**を奏でるこのアンプが、これから先どんな音楽シーンで活躍していくのか非常に楽しみですね。

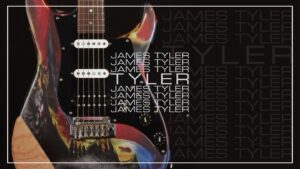




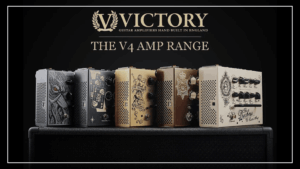

| チャージ金額 | 通常会員 | プライム会員 |
|---|---|---|
| 5,000円〜 | 0.5% | 1.0% |
| 20,000円〜 | 1.0% | 1.5% |
| 40,000円〜 | 1.5% | 2.0% |
| 90,000円〜 | 2.0% | 2.5% |
\ 早く始めるほどお得が積み上がる /
コメント