ALBIT (1) BEHRINGER (1) Benson Amps (2) Blackstar (3) Bogner (4) BOSS (5) Cornerstone (3) Crazy Tube Circuits (4) Darkglass Electronics (2) DigiTech (1) Dumble (2) E.N.T EFFECTS (2) EarthQuaker Devices (2) electro-harmonix (7) Empress Effects (2) Eventide (1) EVH (2) Fender (8) Free The Tone (3) Friedman (3) Fryette (2) Fulltone (1) Gibson (1) Henriksen (1) HOTONE (4) IK MULTIMEDIA (4) Jackson Audio (1) James Tyler (1) JHS PEDALS (3) Keeley Electronics (8) KEMPER (3) KERNOM (1) klon (2) Laney (1) Limetone Audio (2) Line6 (5) LPD Pedals (1) Mad Professor (1) Magnatone (2) Marshall (5) MESA/BOOGIE (3) Morgan Amplification (1) Morningstar (1) MXR (2) Neural DSP (3) One Control (3) Origin Effects (1) Ovaltone (2) Paul Reed Smith (5) Pedaltrain (1) Positive Grid (2) Revv Amplification (1) Science Amplification (1) Soldano (2) strymon (8) Suhr (7) Sunfish Audio (1) Supro (2) tc electronic (5) TECH21 (1) Tom Anderson (1) Tone King (1) TONEX (2) Two Notes (1) Umbrella Company (1) Universal Audio (4) VALETON (1) VEMURAM (7) Victory Amps (3) Virtues (3) Vox (1) WALRUS AUDIO (4) Wampler (6) Warm Audio (3) Xotic (10) YAMAHA (2)
【徹底比較】Nano Cortex vs Quad Cortex|Neural DSP発次世代プロセッサーのどちらを選ぶ?【評判・特徴】

Neural DSPから登場した話題のコンパクトプロセッサー「Nano Cortex」。
「兄貴分」であるQuad Cortexとの違いが気になっている方も多いのではないでしょうか?
どちらもNeural Capture対応で最高峰の音質を誇るプロセッサーですが、サイズも操作性も大きく異なります。
- 「どっちが自分に合っているのか分からない」
- 「両者の違いをちゃんと知ってから買いたい」
そんな悩みを持つ方に、本記事ではNano CortexとQuad Cortexを徹底比較します。
音質、サイズ、操作性、キャプチャー性能、ライブ・宅録での使いやすさ、そして価格まで。
メリット・デメリットやリアルな口コミも交えながら、あなたにとって最適な1台を見極められるよう、詳しく解説していきます。
Nano Cortex vs Quad Cortex|製品概要を比較
スペック比較表
 |  | |
|---|---|---|
| モデル名 | Nano Cortex | Quad Cortex |
| サイズ | 約14.4×10.3×6.2cm | 約29×19×5cm |
| 重量 | 約620g | 約1.95kg |
| 操作方法 | ノブ+ボタン操作 スマホアプリ連携 | タッチパネル フットスイッチ11基 |
| キャプチャー対応 | ||
| USB I/F | 4in / 3out | 8in / 8out |
| 価格帯 | 約29万円 | 約9.9万円 |
Quad Cortexとは?(フラッグシップモデル)

- 7インチのタッチパネル搭載、直感操作が可能
- 最大90種以上のアンプ、100種以上のエフェクトを内蔵
- Neural Captureで自分のアンプ/ペダルを再現可能
- USBオーディオI/F(8in/8out)搭載で宅録にも対応
- フットスイッチ11基でライブも1台で完結
- 実勢価格:約29万円前後(税込)
Neural DSPが2021年に発売したフロア型のマルチプロセッサー。
圧倒的な音質と拡張性を武器に、多くのプロミュージシャンに愛用されています。
Nano Cortexとは?(小型モデル)

- Quad Cortexと同じNeural Captureエンジンを搭載
- サイズはわずか14.4×10.3cm、重さ620g
- 本体操作は最小限、スマホアプリ(Bluetooth)連携で編集
- キャプチャー再生+5つの内蔵エフェクトでシンプルな音作りに最適
- USBオーディオI/F(4in/3out)で宅録にも◎
- 実勢価格:約9.9万円前後(税込)
2024年に登場した、Quad Cortexの“弟分”とも言えるモデル。
必要な機能だけに絞り、手のひらサイズで驚異の音質を実現しています。
Nano Cortex vs Quad Cortex|特徴・機能を比較
サイズ・携帯性・設置性の違い

| Nano Cortex | Quad Cortex |
|---|---|
| 約14.4×10.3×6.2cm | 約29×19×5cm |
| 約620g | 約1.95kg |
Quad Cortexは“据え置き”前提の万能機
- ペダルボードの中心としての存在感
- 厚みもあるため「床置き」での使用が基本
- 頑丈な筐体でツアーやライブの現場にも耐える設計
- モニターの角度やスイッチの配置も“操作しやすい前提”で構成
Nano Cortexは“どこでも使える”超軽量モデル
- ギターケースのポケットや小型バッグにもすっぽり
- スタジオ、リハ、ホテル、自宅練習、どこでも活躍
- デスクトップ使用にも最適(USBバスパワー対応)
- セッションや飛び入りライブ用の“非常用リグ”としても◎
入出力端子・接続性を比較
| Nano Cortex | Quad Cortex | |
|---|---|---|
| 楽器入力 | 1(TS) | 2(XLR/フォーン兼用) |
| キャプチャー専用入力 | 1(XLR/TSコンボ) | なし(共通) |
| 出力 | TRS×2(ステレオ) | XLR×2 + TRS×2(合計4ch) |
| エフェクトループ | なし | 2系統(Send/Return) |
| ヘッドフォンアウト | 3.5mmミニ | 標準ジャック |
| MIDI端子 | TRS IN(EXP兼用) | IN/OUT/THRU(DIN) |
| USBポート | Type-C(4in/3out + 給電) | Type-B(8in/8out) |
| ファンタム電源 | ○(入力対応) | ✕(別途プリ必須) |
Quad Cortexは“接続なんでも対応”型

- **ステレオ出力 ×2系統(TRS+XLR)**でライブ・PA直結も余裕
- FXループ2系統で4ケーブル・メソッド、外部ペダルも自在に組み込み可能
- ファンタム対応XLR入力で、マイクキャプチャーにもそのまま対応
- USBオーディオ8in/8outで宅録・DAW連携もプロレベル
- MIDI制御もフルスペック(DIN接続)で、拡張性も抜群
Nano Cortexは“必要十分”のミニマル設計

- 入力はシンプルに1系統だが、別途キャプチャー専用端子を用意
- TRSステレオ出力はバランス対応でPAにも直結可
- USB-C経由で給電可能、電源アダプター不要の場面も
- ヘッドフォン端子あり、自宅練習・チェックにも使いやすい
- MIDIはTRS端子1つ。省スペースだが、少し工夫が必要
操作性・ユーザーインターフェースの違い
| Nano Cortex | Quad Cortex | |
|---|---|---|
| ディスプレイ | なし (LEDインジケーターのみ) | 7インチ タッチスクリーン |
| 本体ノブ・ボタン | パラメータノブ×5 小型ボタン×5 | 回転式フットスイッチ(兼ノブ)×11 VOLUMEノブ等 |
| スマホ連携 | 必須 (Bluetoothアプリ操作) | 必須ではない (本体完結) |
| エディタ環境 | Cortex Cloudアプリ(iOS/Android)必須 | タッチ操作で全機能にアクセス PCエディタは開発中 |
| 視認性 | 3.5mmミニ LEDによる点灯表示・色で操作誘導 | 非常に高い (カラーUI、階層ナビ) |
Quad Cortexの操作性は“ハード完結型”
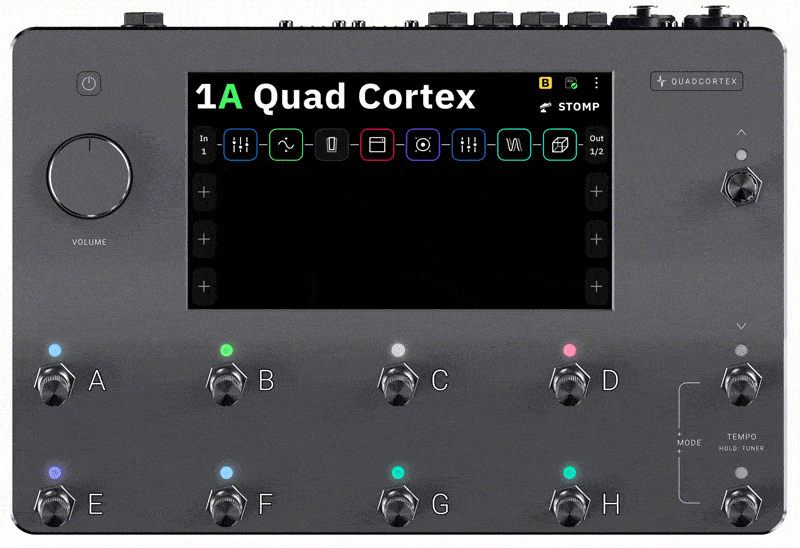
- 7インチの大画面タッチパネルで、スマホ感覚の編集
- 各スイッチがノブにもなる構造で、手元でパラメータを直感調整
- アプリに頼らず本体だけで完結するため、現場での操作も安心
- ライブ前の微調整・ルーティング修正もその場で完了
- Wi-Fiでクラウド連携・ファーム更新も可能
Nano Cortexの操作性は“モバイル連携特化型”

- 画面なし・ノブ5つのみという超ミニマル構成
- 本体操作は最低限(音量やEQの微調整)にとどまり…
- 本格的な編集やプリセット管理はスマホアプリから行う
- Bluetooth接続は安定しているが、トラブル時の操作性に注意
- アプリ接続ができないと操作の自由度が極端に制限される
どちらが“使いやすい”かは、スタイル次第
- ステージや現場で機材を直接操作したい
→Quad Cortex - 普段からスマホ/アプリ操作に慣れている
→Nano Cortex - リハやライブ中に画面を見ながら微調整したい
→Quad Cortex - シンプルなプリセット再生中心・演奏に集中したい
→Nano Cortex
アンプ・キャビネット・エフェクト
| Nano Cortex | Quad Cortex | |
|---|---|---|
| アンプモデル数 | 固定なし (ユーザーが追加) | 約90種 (アップデートで増加中) |
| IR(キャビネット) | 約300種+ユーザーIR 256個まで | 約1,000種+ユーザーIR 256個まで |
| キャプチャーデータ | 最大256個保存可能 | 実質制限なし |
| エフェクト数 | 5種(固定) | 約100種以上 |
| 同時使用数 | 5つまで (信号経路は固定) | 複数同時可 (ルーティング自由) |
Quad Cortex は最初から豊富なモデルを内蔵し複雑なルーティングが可能。
Nano Cortex は「自分で欲しい音だけを入れていく」シンプルスタイル。
プリセットとシーン切り替えの柔軟性
| エフェクト | Nano Cortex | Quad Cortex |
|---|---|---|
| プリセット保存数 | 最大64個 (4つを即切替) | 実質無制限 (バンク・セットリスト管理) |
| スナップショット シーン | 非搭載 (4プリセットで代用) | 最大8つ (1プリセット内) |
Quad Cortex:ライブでの多彩な切替に最適
- スイッチ1つで複数エフェクトを切替える「シーン」機能が便利
- セットリスト管理ができるので、曲ごとの構成も簡単に整理できる
- フットスイッチ11基で操作に困らない
Nano Cortex:必要最低限の切替に特化
- プリセット4つを即座に呼び出せる「4プリセットモード」
- フットスイッチ2基の中に、必要な役割を割り当てて使う構成
- MIDI対応で、外部スイッチと連携すれば柔軟性アップ
USBオーディオ&宅録性能
| エフェクト | Nano Cortex | Quad Cortex |
|---|---|---|
| USB端子 | Type-C | Type-B |
| 入出力チャンネル | 4in / 3out | 8in / 8out |
| クラスコンプライアント | ○ | ○ |
| バスパワー動作 | ○(5V/1.5A以上) | ✕ |
Quad CortexはDAWとの完全連携型
- マルチチャンネル録音、リバンプ、ルーティング分岐が可能
- ASIO対応で低レイテンシーも強み
- 宅録〜スタジオまでプロ品質を追求できる
Nano Cortexは“コンパクトI/F”として優秀
- DI録り、ステレオ出力、ヘッドフォン練習までこれ1台
- 小型のオーディオI/Fとしても十分な性能
- USB-CでPCやiPadとの接続もスマート
Nano Cortex vs Quad Cortex|メリット・デメリット
Quad Cortexの場合

メリット
- オールインワン性能
アンプモデルからエフェクト、オーディオI/Fまで一括して備え、追加機材なしで完結。
1台であらゆる音作りに対応できる安心感があります。 - サウンドクオリティ
Neural DSPの最先端技術により、非常にナチュラルでリアルなアンプサウンドと高品位エフェクトを両立。
プロも納得の音質で、そのままレコーディングにも使える。 - 強力なキャプチャー機能
Neural Captureにより、お気に入りのアンプやペダルを自分でプロファイリング可能。
Nano Cortexとのキャプチャー互換性も高い。 - 操作の直感性
7インチのタッチスクリーン+回転スイッチで、複雑な設定もスマホ感覚で編集可能。 - ライブでの柔軟さ
シーン機能・11基のフットスイッチにより、多彩な音色切替やエフェクト操作が自在。
足元だけでライブが完結できる。 - 将来性と拡張性
継続的なアップデートで新機能やモデルが追加され、Neural DSPのプラグインとも連携可能。 - プロの信頼性
多くのプロギタリストが導入しており、ツアーやレコーディングでも使用実績多数。
デメリット
- 価格が非常に高価
約30万円と、趣味用途には躊躇する価格帯。 - 機能過多になりがち
全機能を使いこなすには習熟が必要。
「宝の持ち腐れ」に感じるユーザーも。 - サイズはそこそこ大きめ
Nanoに比べれば大きく、軽量志向のプレイヤーには不向きな場合も。 - ハードウェア初期不良の例も(改善済み)
スイッチの緩みやUSB接続不良など、初期ロットに不具合があったという報告が一部であった。
Nano Cortexの場合

メリット
- 圧倒的なコンパクトさ・軽量性
手のひらサイズ・600g台。
ギグバッグやポケットに入れて持ち歩ける。 - Quadと同等のサウンド品質
キャプチャー音はQuadと同じ品質。
小さくても音に一切妥協なし。 - 操作がシンプルで分かりやすい
最低限の操作で高品位なサウンドが作れる。
プリセットやEQも本体ノブで簡易調整可能。 - USBオーディオI/F機能も完備
宅録用としてもそのまま使える。 - お気に入りのペダルとの相性抜群
既存ペダルの“アンプ部分”だけを置き換えられる。 - 価格が比較的手頃(約10万円弱)
Helix Stompなど他社競合と同程度であり、コストパフォーマンスも良好。
デメリット
- エフェクトが5種類しかない
ディストーションや複雑な空間系は非搭載。
他のペダルと組み合わせる前提。 - シグナルチェーンが固定
プリFX → キャプチャー → IR → ポストFXという順番を変更できない。 - 画面がないためスマホ必須
操作やプリセット管理には「Cortex Cloud」アプリが必要。 - Bluetooth接続が頼みの綱
BT不良時にはファーム更新ができず、実際に接続トラブルの事例もあり。 - ライブ運用は機能的にやや制限あり
フットスイッチは2つのみ。
プリセット切替が中心で、細かな操作にはMIDIなど外部機器が必要。 - 「思ったよりできないことが多い」という声も
マルチエフェクターと勘違いして購入すると後悔する可能性もある。
Nano Cortex vs Quad Cortex|口コミ・評判
Quad Cortexの場合
ポジティブな評判
- 「タッチパネルでの操作が快適すぎる。他のマルチには戻れない」
編集がスピーディで、直感的。ライブ現場でも素早くセッティング変更ができると好評。 - 「ファクトリープリセットが即戦力。買ってすぐ良い音が出せた」
特にアンプトーンに関して、即ライブやレコーディングで使えるレベルという声が多い。 - 「レコーディングで実機アンプと並べて録っても違いが分からない」
DIトーンとIRの完成度が高く、ミックスで浮かない自然な音像が出せる。 - 「アンプレスでのライブが成立した」
プロの現場でも使用例が急増中。ミュージカル、フェス、バックバンドなどでの採用が報告されている。 - 「頻繁なアップデートで常に進化している」
新機能の追加や音質チューニングが続き、買った後も価値が上がっていくと評価されている。
ネガティブな評判
- 「高い。とにかく高い」
約30万円という価格は、アマチュアには重い負担。「買うか2週間悩んだ」という声も。 - 「多機能すぎて使いこなせない」
あれもこれもできる反面、自分の使い方にはそこまで要らなかった…という中級者の声も。 - 「初期不良報告があった」
一部のユーザーから、フットスイッチの不具合やUSB接続の認識エラーといった報告があった。(発売当初) - 「PCエディタがまだ無い」
2025年時点では、スマホアプリはあるが、PCで操作したいユーザーには不満あり。 - 「HelixやKemperと比べて合わないという人も」
ハイゲインや特定の音作りで、「他社の方が自分の好みに合っていた」との比較コメントも。
Nano Cortexの場合
ポジティブな評判
- 「音がQuadとまったく同じ。小さくても妥協なし」
キャプチャーのクオリティはフラッグシップと同等と太鼓判を押されている。 - 「このサイズ感が最高。ギターケースに入るのが嬉しい」
モバイル性に惹かれて購入したユーザーから、機動力の高さが称賛されている。 - 「宅録にちょうど良い。USB I/Oが優秀」
DI録り、DAW接続、ヘッドホン練習までをコンパクトにこなせる点が高く評価されている。 - 「ペダルボードの“アンプ”として最高」
歪み系ペダルを前段に置き、NanoをIR & キャプチャー再生機として活用するスタイルが定着。 - 「必要なことだけできて、操作が簡単」
「Quadは難しすぎたけどNanoは直感的に使える」という声もあり、シンプルさが支持されている。
ネガティブな評判
- 「エフェクトが少なすぎる」
Chorus、Delay、Reverbしか無く、歪みやフィルターを内蔵していない点に不満の声も。 - 「キャプチャー順が固定、信号の自由度が無い」
プリFX→キャプチャー→IR→ポストFXという流れしか組めないのが不自由だという意見。 - 「スマホアプリ必須なのが面倒」
編集やプリセット保存にアプリが必要で、「Bluetoothが無いと何もできない」と批判する投稿も。 - 「Bluetooth不調報告」
接続できない・ペアリングに失敗するといった報告が散見され、信頼性に疑問を持つユーザーも。(初期のトラブル) - 「“マルチ”だと思って買うと後悔する」
キャプチャー再生+最低限の空間系しか無いため、「万能マルチ」と勘違いして買うと失望するというレビューも。
Nano Cortex vs Quad Cortex|用途別のおすすめ
Quad Cortexをおすすめできる人

- プロ志向・上級者
ステージやスタジオで一切妥協のない音作りを求めるギタリスト。
豊富なアンプ/エフェクトで細部までトーンメイクしたい人や、機材の能力をフル活用できる上級者に最適。 - ライブで多彩な演出をする人
1曲の中でクリーンからハイゲイン、エフェクト盛り盛りまで何段階も音色を切り替える必要がある人。
シーン機能と豊富なフットスイッチが大活躍。 - 宅録・DTMヘビーユーザー
DAWと連携しながら録音や再アンプ、マルチトラック処理をしたい人。
USB 8in/8outで、オーディオI/Fとしても完成度が非常に高い。 - アンプ/エフェクターコレクター
いろんなアンプモデルやエフェクトを試して遊ぶのが好きな人。
90種以上のアンプと100種以上のエフェクトを内蔵、プラグイン連携も可能で可能性は無限大。 - バンドのサウンドを支える人
バンドでギターが1人だったり、サウンドの主軸を担う役割の場合。
出音の安定性・可搬性・操作性を考えると、Quad Cortexが安心。
Nano Cortexをおすすめできる人

- シンプル志向の中級者
「良いアンプトーンが1つあればOK」という考えのプレイヤー。
音作りに時間をかけたくない、だけど音質には妥協したくないという方に最適。 - お気に入りのペダルを活かしたい人
すでに歪みや空間系など手持ちペダルがある人は、アンプ&キャビ部だけNanoに任せることで音作りを軽量化・高品質化できる。 - 機材を減らして身軽にしたい人
大きなアンプや重いボードの持ち運びがしんどくなった方へ。
Nanoならギターケースのポケットに入れて、PA直でライブも可能。 - 予算を抑えたい人
Quad Cortexほどの予算は出せないが、音質では妥協したくない。
「10万円以下でNeural DSPサウンドを手に入れたい」なら最適解。 - 宅録初心者〜中級者
自宅で録音・ヘッドフォン練習・YouTube制作をしたい人。
複雑なオーディオルーティングやドライバ設定が不要で、USB接続だけで完結できるのが魅力。 - シンプルなライブをする人
足元で多くの操作をせず、プリセット切替で完結するようなライブスタイルに。
2〜4音色で十分な構成なら、Nano Cortex単体でも十分対応できる。
初心者には?
結論として、全くの初心者にはNano CortexもQuad Cortexも少し難しいかもしれません。
ただし「最初から“本物”を使って始めたい」という意志のある方なら、Nano Cortexはおすすめできます。
プリセットをスマホで管理し、シンプルな操作で即ハイエンドなサウンドを得られる点は、上達にもつながります。
一方、Quad Cortexは情報量も機能も多く、最初の1台としてはやや重すぎる可能性があります。
まずはNano Cortexや他のマルチで経験を積み、必要に応じて将来的にQuad Cortexへ…というステップアップが現実的です。







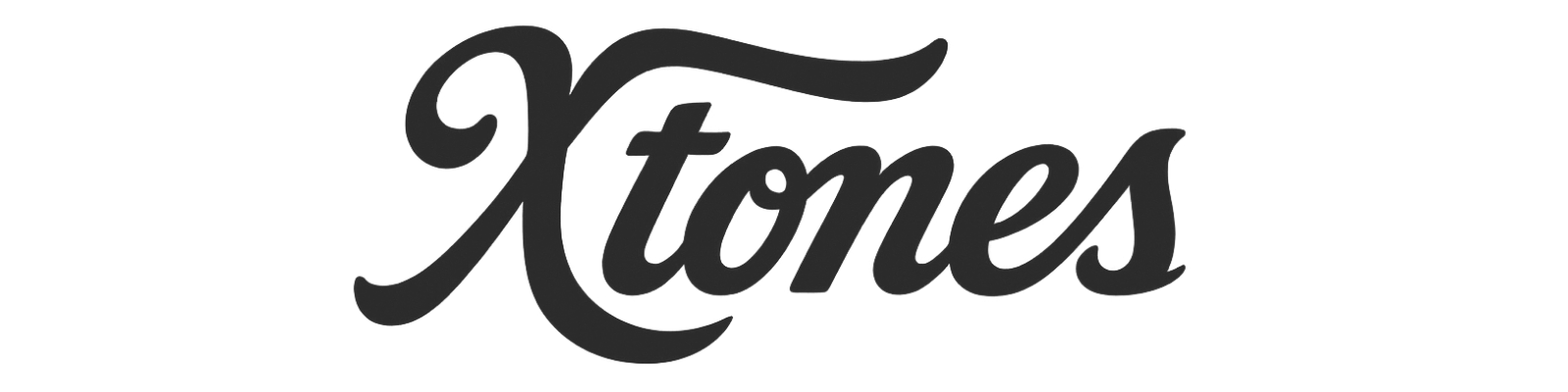










コメント